皆さん、こんにちは!今回も我が家の引っ越し体験について振り返っていきたいと思います。
前回の記事では”住宅購入”における、物件を選ぶ時に確認や事前に実施をおススメする“住宅ローンの事前審査の申請”、“周囲環境の確認”、“近接道路の確認”、“敷地境界線の確認”、“第三者への相談”などについて、ご紹介しました。
↓↓前回の記事↓↓
さて今回はいよいよ【住宅購入編】の最後の記事になります。
ここまでは住宅探しを中心にお伝えした記事の内容となっていましたが、最後は中古住宅購入における“売買契約”や“住宅ローン申込み”や“引渡し”について、不動産仲介業者とのやり取り、住宅ローン融資における銀行との手続き、行政手続き等について体験を踏まえながらご紹介したいと思います。
それでは紹介を始めます!
中古住宅購入における一般的な事務手続きの流れについて
まずは簡単に中古住宅購入における事務的な手続きの流れについてご説明します。
※リフォームの契約関連については今回は省きますが、引っ越しを急ぐようであれば住宅購入と同時進行で契約を進めていく必要があります
具体的には以下の流れとなります。
①購入したい物件の購入申込書を提出
②住宅ローンの事前審査を申し込む
③約2週間後、重要事項説明を受けて売買契約を結ぶ
④住宅ローンの本審査を申し込む
⑤約1か月後、住宅ローン契約締結
⑥約1~2週間後、融資実行・決済・登記・引き渡し
こうして見ると、①~⑥の完了まで約2ヵ月の期間が必要であることがわかります。
どんなに急いで引っ越したくても、住宅の購入においては最低これくらいの期間を要するということです。
次に具体的に①~⑥の詳細についてご紹介していきます。
①購入したい物件の購入申込書を提出
気に入った物件を見つけたら不動産情報ポータルサイト等を利用して住宅の内見を実施します。
内見を実施して住宅の購入の意志が固まったら、不動産会社を通して売主に購入申請をします。
不動産業者によって多少、書式は異なりますが購入申込書に購入の意思を記入します。
具体的には以下の内容です。
■氏名
■現住所
■購入金額
■手付金
■引渡し希望日
■建物状況調査の希望有無(買主負担)
記入する内容の内、購入金額や引渡し希望日等はあくまで希望条件となります。
購入申込書に記載した内容をもとに不動産会社が売主と交渉し、条件を調整することになります。
同時期に別の買主から購入申込書が提出されてそちらの方が条件が良かったり、あまりにも低い購入金額や直近の引渡し日を希望すると、交渉すらしてもらえなくなる可能性があります。
実際、私は別の記事で紹介した物件Aの購入申込書についてネット上の金額よりも200万程度値引きした金額を記載して、第2申込者であったことも重なって門前払いとなりました(笑)
売主や不動産会社との駆け引きが購入申込書には集約されています。
希望条件を伝えることも大事ですが、なるべく常識の範囲内で条件を記入して希望の物件を手放さないように注意しましょう。
仮に交渉失敗となったとしても今回は縁がなかったと割り切る事が大切です。
その場合は頭を切り替えて、また新たな物件を探索しましょう。
②住宅ローンの事前審査を申し込む
もしここまでに住宅ローンの事前審査を受けていない場合は、住宅ローンの事前審査を申し込みましょう。提出時期は購入申込書の提出と同時となります。
住宅ローンは昨今、様々な金融機関や申し込み形態があり、どれを選択するかは買主の判断に委ねられます。
具体的には以下のとおりです。
■都市銀行(メガバンク)
■地方銀行
■信用金庫
■ネット銀行
■フラット35
借入条件や金利やオプション(保障)などを自身でしっかりと調べた上で、自分の希望に合う金融機関を絞り込みましょう。
現段階では売買契約を結ぶことを優先して、不動産紹介の金融機関で事前申込を実行してもOKです。住宅ローンの本審査までに第一希望の金融機関に改めて同条件で事前審査を申し込んで問題なければ、そちらの金融機関で本審査に進んでも構いません。もちろん、同時に複数の金融に事前審査を依頼してもOKですが、せいぜい2~3社に留めておきましょう。あまりにも多くの金融機関に事前審査の依頼をかけると、各金融機関はあなたが、いくつの金融機関に事前審査を依頼しているか把握できるシステムとなっているので、借入の意思なしとして、不合格の烙印を押されてしまう可能性もある為です。
ネット銀行であれば早くて当日、他の金融機関も2〜4日ほどで審査結果が通達されます。
事前審査で申請する金額は物件価格におおよその諸費用を加算した額として下さい。こちらの額については、本審査時や契約時に若干の変更はおそらく可能です(金融機関によっては不可かもしれませんが)ので、諸経費が曖昧な場合は少し多めに申請することをおススメします。
もし事前審査に落ちてしまった場合は、他の金融機関に申し込むことになりますので、いくつか金融機関の候補を準備しておく事で次の申込みがスムーズに行えます。
ただし、他の金融機関にて事前審査を受けなおしている間に、同じ物件を購入希望の他の方が先に事前審査に合格した場合は、そちらの方に物件を取られてしまうリスクがある事を理解しておいて下さい。
ちなみに、みずほ銀行などではインターネット上で、AI事前診断などを実施する事が可能ですが、この診断の結果を持って不動産会社から事前審査OKの烙印をもらえるかは不明です。(私の時はダメでした)
③重要事項説明を受けて売買契約を結ぶ
金融機関による事前審査に無事に合格した時、他に購入の意思のあるライバルがいない場合は、あなたは売買契約を締結する事が可能となります。
ここまで来て購入をお断りする事はまずないかと思いますが、もしキャンセルする場合はここが境界ラインとなります。
ここから先は手付金(通常は約5~10パーセント程度)をお支払いするので、買主の都合で特定の条件(住宅ローンの本審査に落ちた場合や買主が死亡した場合等)を除く理由で売買契約を破棄した場合は、高額な手付金が戻って来ないことになります。逆に売主都合で売買契約を破棄した場合は、あなたが支払った手付金額の倍額があなたの銀行口座に振り込まれるのが通例です(宅建業法にて定められています)。
また、事前審査を受けて購入申込書も提出したにも関わらず物件をキャンセルするような買主は不動産会社からの信頼を失って敬遠される可能性が高く、今後の物件探しが難しくなることもあるのでご注意下さい。
購入する意思に変わりがない場合、不動産会社と買主で双方に調整した日時にて、不動産会社又は現住所の自宅などで宅地建物取引士から重要事項説明を受ける事になります。
売買条件・物件情報・売主との取り決め事項などの内容(基本的には内見時や購入申込書の提出時に一度は説明を受けた内容のはずです)をしっかり聞いておきましょう。
我が家の場合は、今後のリフォーム記事でご紹介しますが、備え付けのBOSEスピーカーやエアコンや家具などの一部を売主が処分するという事でしたので、そのまま置いておいてもらうことになっていたのですが、しっかりとその旨が重要事項説明の一部として記載されておりました。
重要事項の説明内容に問題がなければ、売買契約書に捺印をして売主と売買契約を結びます。
売買契約の締結後、速やかに手付金を支払う(多くの場合は指定口座への振り込み)必要があるので、事前に金銭の準備をしておき支払いの忘れがないようご注意下さい。
④住宅ローンの本審査を申し込む
売買契約の締結と同じタイミングにて、事前審査に通過した金融機関(複数の場合は、どこか1社に絞る必要あり)に住宅ローンの本審査の依頼を行ってください。
不動産会社から紹介頂いた金融機関であれば、不動産会社が窓口となって今後の住宅ローンの本審査の申し込みや必要書類の取りまとめなどフォローをしてもらえる事が通例です。
しかし、不動産会社とは無関係の金融機関(ネット銀行など)へ本審査を申し込む場合は、全てご自身で住宅ローンの契約から融資実行まで、該当の金融機関の担当者とやり取りしながら進めていくことが必要となります。
本審査では、以下のような書類を提出することになります。
・実印
・印鑑証明書
・住民票
・収入印紙
・売買契約書
本審査には1〜2週間ほどの期間が必要となりますので、売買契約締結後すぐに申し込むことが買主・売主双方にとってもベターな進行であるかと思います。
売買契約を締結するまでに必要な書類は事前に揃えておくことでスムーズに手続きを進めることが可能です。
この段階で別の金融機関に事前審査を新たに申請することも可能ではありますが、あまりにも時間を多く掛けてしまうと引渡しに遅れが生じるだけでなく住宅ローン特約がない場合は契約不履行として手付金を手放さなければならない可能性も最悪の場合はありますのでご注意下さい。
事前審査に通過していれば本審査には基本的には通ることになりますが、既往症などで団体信用生命保険※への加入ができなければ審査に落ちることもあります。
※団体信用生命保険(以下、団信)とは、住宅ローン契約者に万一のことが起きた時は保険会社が住宅ローン残高を保障してくれる制度です。住宅ローンの融資を受ける為には団信加入(保障の範囲は金融機関によって異なりますが50%保証ではある事が多いです)が基本的には必須となっています
健康面に不安がある方は、ワイド団信への加入や団信不要のフラット35の利用が優先的な選択しの一つになってきます。
団信や住宅ローンの種類については詳細はこのブログでは紹介しませんので、詳しく知りたい方は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索してご確認下さい。
ここからは私自身の体験談ですが、以前お伝えした過去にマンション購入時は全国区の大手企業所属だったので、自身の信頼力も高く都市銀行でも余裕で好条件で事前審査に合格していました。
しかし今回の中古住宅購入時は、会社の規模としてはそこそこの地方の企業に所属しており、都市銀行の事前審査は通っても、貸入の金利条件などは優遇が少ないように感じました。
例えば、M銀行のAI事前審査に諸条件を記入して申請してみたところ、すぐに結果が出て60~80%融資実行可という結果でしたが、いざ本審査に進もうと銀行に問い合わせて見ると、融資実行まで最低2ヵ月半かかる・金利の引き下げが最大ではない(条件は悪い)などと強気で言われて、少しムッときました。
結論、今回の中古住宅購入における住宅ローンは、不動産会社のご紹介頂いた地方の金融機関(某農業協同組合)にお願いしました。
理由としては、こちらの金融機関は金利の上乗せなくオプションの3大疾病病100%保障を付属できるキャンペーン中であり、金利の引き下げ後のパーセンテージそのものは他の金融機関には劣るもののオプションを含めたトータルの金利が比較的優れており、融資実行までの期間も短かった為です。
地方民においては、もしかしたら都市銀行よりも地方の金融機関の方が条件が良くなる可能性があるのでかもしれません。ただし地方銀行は金利が高めでした。
また、ネットの住宅ローンについても検討しましたが、確かに見た目上は圧倒的に低金利なのですが、特定の携帯キャリアの契約が必要であったり、プラスアルファで別のカードローンや別のサブスク月額料金の支払いが発生するなど、メリットは意外と少ないように感じました。
⑤住宅ローンの契約締結
無事に本審査にも通過して融資の内定をもらえたら、次は住宅ローンの融資を受ける為の準備に取り掛かります。
借入先の金融機関にもよるかもしれませんが、融資を受ける前に最低一度は最寄の支店に赴むいて融資申し込みを進めることになるかと思います。
この時の申し込みで金融機関と締結する契約を『金銭消費貸借契約(通称:金消契約)』といいます。契約時には契約者本人はもちろん、連帯債務者や保証人の同席も必要です。
金消契約に関わる全ての人がそろった上で、重要事項の説明を受け契約内容を確認し、契約書への署名捺印を実施します。契約締結後に誤りを見つけても訂正できませんので気付いた点があれば署名捺印の前に修正・確認を徹底しましょう。
融資申し込みで具体的に決めていく内容
融資申し込みで具体的に決めていく内容は以下の通りです。
・貸入額
・貸入年数
・適用金利
・返済方法(元利均等返済と元金均等返済)
・オプション(3大疾病100%保障団信などの追加保障)加入の有無
・新規口座開設(又は既存口座の確認)
上記について簡単に説明すると、まず貸入額については事前審査・本審査よりも精度を上げた最終の貸入金額を決定させます。具体的には登記費用、火災保険の料金、住宅ローン保証料や手数料、固定資産税の日割り清算金、印紙税、仲介手数料となります。
リフォーム費用や家具家電代については基本的には住宅ローンに含めることはできませんが、融資いただく金融機関に相談することで含めてもらえる可能性もありますので、まずは相談してみて下さい。ちなみにリフォーム費用を住宅ローンに含める場合は金利が高くなってしまうことがあります。また、リフォーム費用を単独でローンを組む場合も住宅ローンよりも金利が高い傾向です。
次に貸入年数については、住宅ローンを何年で返済するかを決めていきます。返済期間が短ければ、毎月の返済額が高くなりますがトータルで返済する金額は若干安くなります。逆に返済期間を長くすれば、毎月の返済額を抑えることができますがトータルの返済金額は若干高くなってきます。ご自身の収入や年齢により適切な返済期間を設定しましょう。
続いて適用金利については、変動金利・固定金利に関わらず住宅ローン融資実施日の店頭金利が適用され、そこから人によって引き下げ金利分が減算された数値が最終の金利となります。融資申し込み日に対して融資実行日が翌月に跨ぐ場合は、店頭金利や基本引き下げ金利が上下する可能性があることを認識しておいてください。ちなみに引き下げ額については、就業先や年収や返済能力によって優遇される金利が変わってきます。
返済方法は、元利均等返済と元金均等返済の2つから選択する形となります。多くの方は毎月の返済額が安定している元利均等による返済が推奨されます。しかしある程度の余裕のある収入がある場合は元金均等による返済方法の方が、当月の金利に左右されて返済額の変動こそ発生するものの元金がどんどん減っていきますので、金利分の支払い分が毎月徐々に減っていきます。結果、元金均等返済の方がトータルの支払い額は少なくなります。元利均等返済と元金均等返済の詳細については他サイトでも詳しく紹介されていますので、別途検索をお願いします。
オプション加入の有無については金融機関によって適用できるオプションが様々です。強制加入となる通常の団信(死亡、高度障害)以外で、3大疾病保障(がん、脳卒中、急性心筋梗塞)の保障や8大疾病保障(3大疾病に加えて糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、肝疾患、慢性膵炎)の保障等は金利が0.15~0.30%程上乗せとはなりますが、掛け金の割りにはとても価値が高い保障となります。他にも金融機関によって魅力的な商品がありますので、一度は検討してみた方が良いでしょう。
最後に住宅ローンを返済する金融機関の口座を設定します。すでに融資頂く金融機関の本人名義の口座をお持ちの方は、新規に口座を開設する必要はありません。口座がない場合は平日のどこかで口座開設する作業を求められる場合が常です。
必要書類の準備
融資をスムーズに進める為に、現段階で揃っている書類の先行提出と、今後用意する書類を確認していきます。
具体的には以下の書類などです(金融機関によって異なる可能性もありますので都度ご確認下さい)。
・源泉徴収所
・住民票謄本
・印鑑証明書
・銀行指定申込書
・健康保険証のコピー
・所得証明書
・火災保険の支払い証明(カード利用明細や保険証書の控え)
ただし、ここまでの事前審査や本審査で同じ書類をすでに提出済みの場合は改めて提出する必要はありません。
⑥融資実行・決済・登記・引き渡し
さあいよいよ金消契約の融資の実行日となる住宅の引渡し日を迎えることになります。
同じタイミングで火災保険加入の確認や司法書士立ち合いの元で抵当権設定契約も行われます。
引渡しの実施場所は融資を受ける金融機関で行うことが一般的です。
融資実行時には⑤で紹介した必要書類の内、先行で提出できていない書類や実印を必ず持参して下さい。
融資実行日には、残金決済と物件引渡しを同時に実施するのが通例となります。
そのため売主・金融機関と事前に打ち合わせをし、日時を調整しておく必要があります。
不備なく手続きを進めることができれば融資が実行され、即、購入金額から手付金額分を減算した金額が売主へ振り込まれます。その後、物件の登記と抵当権の設定が司法書士立ち合いの元で実行されたら全ての手続きが完了となり、鍵の引渡しを受けて住宅は売主の所有物となります。
金融機関に指定した口座には住宅ローンで融資して頂いた金額から、手付金額分を減算した住宅の購入金額・登記費用・保証料・銀行手数料・固定資産税等の日割り清算費、印紙代、仲介手数料を引いた金額が残る形になります。
具体的にはすでに支払った手付金額と火災保険の金額がそれに当たります。
まとめ

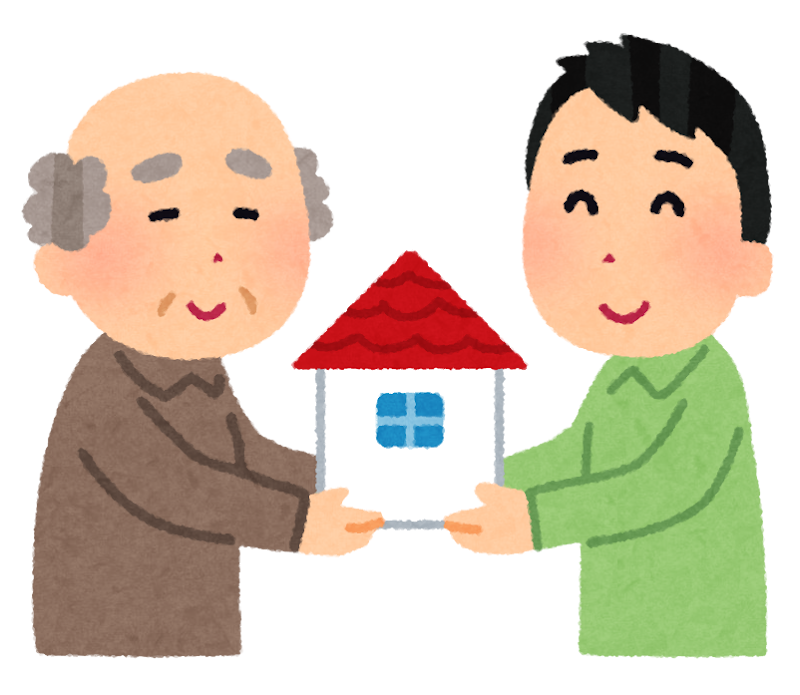
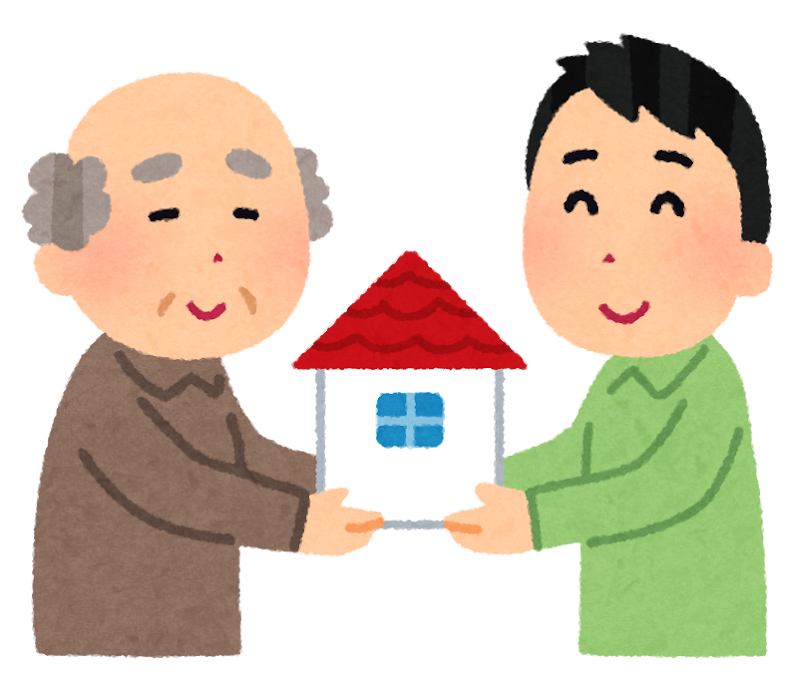








コメント