皆さん、こんにちは!今回も我が家の引っ越し体験について振り返っていきたいと思います。
前回の記事では”新築”と”建売”と”中古住宅”の3択について、そのメリット・デメリットと我が家が今回の引っ越しにおいて“中古住宅の購入”を選択した経緯について紹介させて頂きました。
↓↓前回の記事↓↓
さて今回は、前回“理想の中古住宅”を見つけた我が家ですが、前回の記事では触れていない中古物件を選ぶ時に確認や事前に実施するべきことについて実体験を元にお話ししていきたいと思います。
具体的には“住宅ローンの事前審査の申請”、“周囲環境”、“近接道路の確認”、“敷地境界線の確認”、“第三者への相談”などについて触れていきたいと思います。
“住宅ローンの事前審査の申請”について
土地や住宅を購入する時、ほとんどの方は”住宅ローン”を組んで費用を捻出するのではないかと思います。
我が家も例外ではなく、過去にマンションを購入した時、今回中古住宅を購入した時も共に住宅ローンを申し込んで、購入する住宅を担保にご融資を頂いています。
住宅ローンは、まず事前審査を受けて融資が可能かを銀行に判断してもらい、それで問題なければ住宅の売主と売買契約を結び、料金を支払う為に住宅ローンの本審査に進んで融資を受けます。
事前審査に通らなければ、住宅の売買契約を結ぶことはできません。
住宅ローンの事前審査のタイミングの重要さ
前回の記事で紹介した、築7年中古木造住宅である物件Cの購入申込書を提出した時、2番手の申し込みだったことについて軽く触れました。
この時お世話になった不動産屋さんに推奨頂いた銀行で、住宅ローンの事前審査を購入申込書の提出と同時に実施しました。
一方、1番手の申し込みを行った別の方も同じく住宅ローンの事前審査合格待ちという状態でした。
申し込みの約1週間後、ほぼ同時期にお互い事前審査に合格したようで、1番手の方に決定という結果となりました。
この時は、少し残念な結果になったと思っていました。
(まあそのお陰で購入を決めた住宅に巡り会えたので結果的には良かったのですが・・・)
もし事前審査のタイミングについて、もっと早く申請をして合格していれば、あるいは1番手の方を差し置いて事前審査にすでに合格している我が家が買主となっていた可能性もあります。
住宅ローンの事前審査を先に行っておく事のメリット
上記に説明した通り、事前審査に合格していれば希望する住宅の購入を他の方より有利に進める事ができる可能性が高まります。
事前審査を先に合格しておく事のメリットは他にもあります。
まずは住宅ローンの借入可能額を把握できるという点です。購入する物件の予算を定めやすくなり、物件探しも効率よく進めることが可能となります。もし借入可能額を把握しないまま物件を探すと、予算オーバーや借入可能な金額よりも低い金額の品質の低い住宅を購入してしまうような事象に陥ってしまうかもしれません。
次に住宅購入における資金計画を立てやすいという点です。月あたりの返済金額を把握する事ができるので将来の資金計画をシミュレーションする事が可能となります。これにより将来、安定した無理のない生活が送れる可能性が高まります。
他にも事前審査に通っていることで売主との価格交渉を有利に進められるという利点もあるようです。
事前審査は可能であれば先に申し込んでおきましょう
住みたい住宅を探していて、収入や手持ちの貯金などから自分が借入可能な大体の金額を掴めている場合は、気に入った物件情報をもとに金利等は意識せずにどの銀行でも良いので住宅ローンの事前審査を受けて、住宅購入を有利に進めましょう。
そうすれば時間の猶予ができるので、売買契約を結ぶまでにもっと金利条件の良い別の銀行でも事前審査を受けてみて無事に合格できれば、本審査にはその条件の良い方の銀行で進めばOKです。
ただし借入金額を変えて何度も繰り返して事前審査を受けるのは、住宅ローンの融資を受ける事に対して不利になっていくので、事前審査は多くても3回くらいにしておきましょう。
※銀行は買主が何度、どの銀行で事前審査を行ったか把握できるシステムとなっているようです
“周辺環境の確認”について
次に“周辺環境の確認”を実施する事をオススメします。
一言でオススメと言っても様々な確認するべきポイントがあります。
例えばハザードマップ、夜間の静寂性、道路との近接状況、敷地境界の確認、通勤・通学距離、スーパーの有無等がそれに当たります。
こちらは住宅ローンと違って、物件が変わる度に確認した方が買主にとって安心と納得のできる住宅購入か可能となるでしょう。
3件目、4件目となると「どうせ大丈夫だろう」と確認をサボりガチなりますが、必ず確認して下さい。
周囲環境の確認について、いくつかピックアップしてご説明します。
災害リスク
各自治体では、お住い予定の土地について災害リスク(地震、洪水、土砂災害など)を公表しています。
これをハザードマップと呼びます。
ハザードマップは国土交通省ポータルサイトや各自治体のHPで検索すれば誰でも確認することが可能です。
完全に災害のリスクのない土地などありませんが、例えば水害のリスクが40cmある、のような場合は家の床上が規定の高さよりも40cmを超えてれば、災害リスクがあっても浸水のリスクが少ないという事になります。
災害のリスクに対して、発生の頻度と対策が可能かを考慮して、住宅を決めていきましょう。
住宅に関わるハザードマップの一部についてご紹介します。
洪水ハザードマップ
河川の氾濫などにより浸水が想定される区域を示します。
土砂災害ハザードマップ
がけ崩れ、土石流、地滑りなど土砂災害が発生するリスクのある区域を示します。擁壁で土砂を止め土しているような住宅はなるべく避けましょう。
津波ハザードマップ
地震などにより津波が発生し、浸水が想定される地域を示します。
高潮ハザードマップ
台風などにより高潮や高波による浸水が想定される地域を示します
地震ハザードマップ
近隣状況と夜間の静寂性
近接する道路の状況
1つ、会社の同僚からアドバイスしてもらった内容があります。絶対に大通りに面する住宅はオススメしないと。
理由は言わずもがな、トラックや低音マフラー車や暴走族の通行による騒音や近隣の花火大会などのイベント時に路駐による自身の駐車場への侵入不可などで、強いストレスに悩まされているからとの事でした。
また道路の近接状況確認としては、自宅の駐車場が私道に面する土地や住宅も避けておいた方が無難です。
これは実家が私道に面してるのですが共同私道になっており、実家の前面の傷んでいる雨水側溝の修繕などが勝手には直せなく市にも相談できないのでいろいろと面倒くさい状況だったりするので、私道は避けた方が良いと思います。
私道が砂利道だったりすると砂埃にも悩まされます。
敷地境界線の確認
敷地境界線を住宅購入前に確認することは後々のトラブル発生を未然に防ぎます。
住宅における敷地境界線のトラブルは、隣地の住民との敷地境界位置に対する認識の違い、敷地境界線からの建物や樹木などの越境、境界票がない時の曖昧さ回避、登記上の敷地境界線との差異などが考えられます。
上記に当てはまる土地であれば、物件そのものを変更することをオススメします。
中には自分の敷地を少しでも広くしようと敷地境界線を「昔はこっちんのラインだった」のように勝手な主張をしてくるクレーマーもいるようです。
敷地境界線で揉めたとしても、それを上回る条件の良い住宅でどうしても住みたい場合は、住民同士の話し合いで敷地境界仙の問題を解決できれば良いのですが、解決できない場合は専門家への相談、裁判外紛争解決手続(ADR)などを活用して解決を目指しましょう。
第三者への相談
住宅を決める時、自身や家族だけで決めようとせずに少しでも気になる状況などがある場合は、先駆者にアドバイスを求めることもおススメです。
住宅を探していると「この物件、築年数の割には綺麗で良いな」と思っていた住宅でも、「だけど、この条件だけは少し気になるな・・・」という部分が出てくるはずです。
そんな時に、自身や家族は住宅を買うことが目的になっているので、どうしても良い方にばかり目が行きがちで、悪い方は「まあ、何とかなるか」と目をつぶろうとしてしまいます。
冷静に判断できない状況に陥ることがあるので、そういった場合は住宅購入経験のある第三者に相談してみましょう。
我が家でいうと、先ほど紹介した大通りに面した住宅について、会社の年下の同僚に相談してみましたが、「大通りは騒音や路駐に悩まされるのでやめた方がいい」というアドバイスをもらいました。
また会社の先輩上司には、子供の通学距離について学校から自転車で40分でも大丈夫?という相談をしたところ冷静に「遠すぎるからやめとけ」と助言をいただきました。
第3者から言われると、自分の中でも冷静になって、やっぱりその通りだよなーっと、ちゃんとした判断が可能となります。
自分たちだけで住宅を決めようとすると良い方ばかりに目が行ってしまうので、できれば第3者にアドバイスを求めて冷静な判断をするようにしましょう。

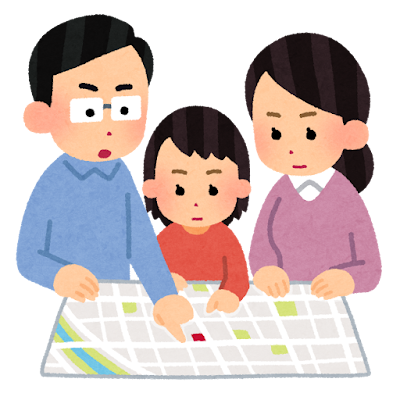



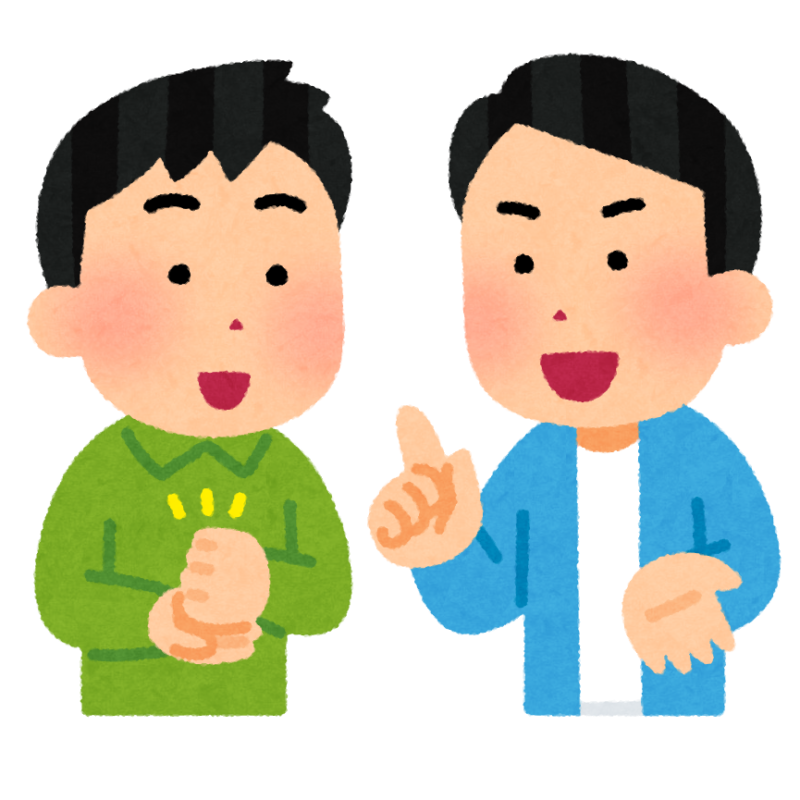
コメント